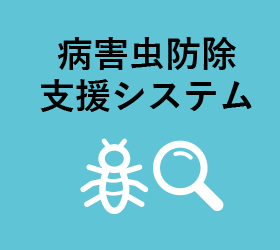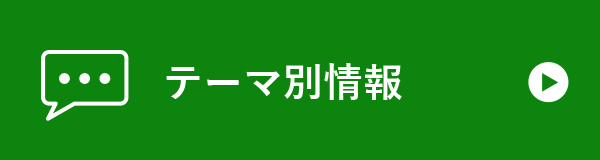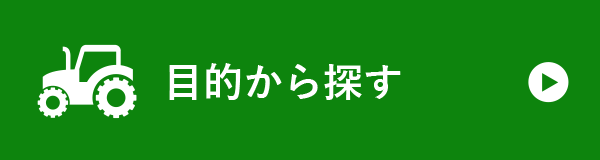ホーム > テーマ別情報 > 安全農産物生産 > 農作物有害動植物発生予察情報 > 2025年度の農作物有害動植物発生予察情報 > 斑点米カメムシ類の注意報発表!!
掲載日: 2025年7月2日
ここから本文です。
斑点米カメムシ類の注意報発表!!
病害虫名
いね 斑点米カメムシ類
対象地域
県下全域
発生量
多い
注意報発表の根拠
- 特別巡回調査(6月30日~7月1日)で実施した畦畔・農道等におけるすくい取り調査(調査地点数:41か所)の結果、斑点米カメムシ類の発生確認地点率は100%、平均すくい取り虫数は82.5頭で、6月後半(6月16~18日)の巡回調査時(発生確認地点率:87%、平均すくい取り虫数:13.5頭)から急激に増加している(図1、2)。
- 特に、畦畔・農道等において、出穂しているイネ科雑草が残存した地点で多く確認され、100頭を超える地点が9地点(22%)で見られた。
- 向こう1か月の気温は高いと予報されており、斑点米カメムシ類の繁殖が活発になると推測される。
防除対策
- 畦畔、農道、休耕田等で現在雑草が繁茂しているところでは、速やかに除草を行う。
- 水田辺の雑草対策は、水稲の出穂期前後に行うと斑点米カメムシ類の水田侵入を助長するため、出穂2週間前(7月中旬頃)までに実施する。また、広域で一斉に実施すると効果が高いため、地域ぐるみで実施する。
- 県内の主要種であるアカスジカスミカメは、イヌホタルイやノビエの穂に産卵し繁殖するため、水田内に残存した雑草対策も徹底する。
- 薬剤散布は穂揃期および穂揃期7~10日後の2回を基本とし、徹底する。出穂期が早まると予想されているので、圃場の出穂状況をよく観察し、適期に薬剤散布を実施する。
- 出穂2週間前(7月中旬頃)以降、やむをえず草刈りを実施する場合は、「山形県病害虫防除基準」を参照し、薬剤散布直前、または、対象薬剤散布後1週間以内に実施する。
↓pdfはこちらをクリック↓
お問い合わせ
関連情報
2025年9月24日令和7年度病害虫発生予察情報(第7号)
2025年9月19日令和7年度病害虫発生速報第11号(園芸作物共通 飛来性害虫)
2025年8月27日令和7年度病害虫発生予察情報(第6号)
2025年8月12日令和7年度病害虫発生速報第10号(ねぎ、えだまめ等 飛来性害虫)