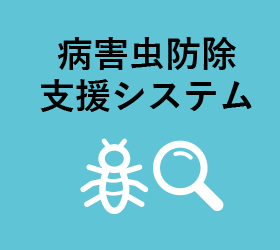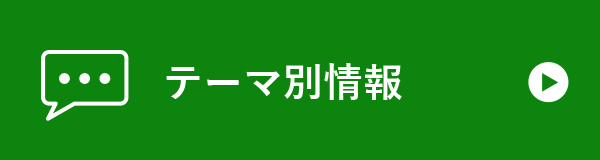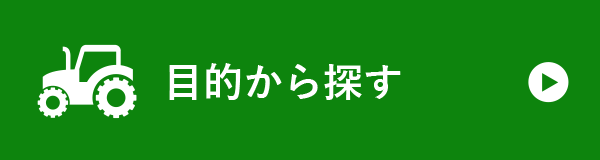ここから本文です。
もも収穫後のせん孔細菌病対策
ももは中生種の収穫がほぼ終わり、晩生種の収穫時期を迎えています。
近年、ももの病気で増加しているのが、せん孔細菌病です。この病気は収穫後の9月以降の秋季の防除がとても重要です。来年の栽培に向けて秋期防除を徹底し、越冬伝染源となる園地内の病原菌密度をしっかりと下げましょう。
具体的には、収穫後にボルドー剤などの無機銅剤を2週間おきに二回から三回散布します。一回目の散布は、収穫後できるだけ早く実施しましょう。また、晩生の品種がある場合には、収穫が終了した樹から防除を行いましょう。なお、使用する薬剤によっては薬害の恐れがあるので、炭酸カルシウム剤を加用します。また、台風の通過等の影響で早期に落葉すると、落葉部位からの感染が多くなります。そのため、薬剤散布は台風の通過や降雨の前に行いましょう。
さらに、耕種的な対策として、風当たりの強い園地では防風ネットを設置します。また、樹勢が弱いと発生が多くなるので、適正な樹勢の維持に努めましょう。
せん孔細菌病は、薬剤だけで防除するのが非常に難しい病気です。春先に行う発病枝の切除など耕種的な手法も組み合わせ、総合的な対策を徹底しましょう。